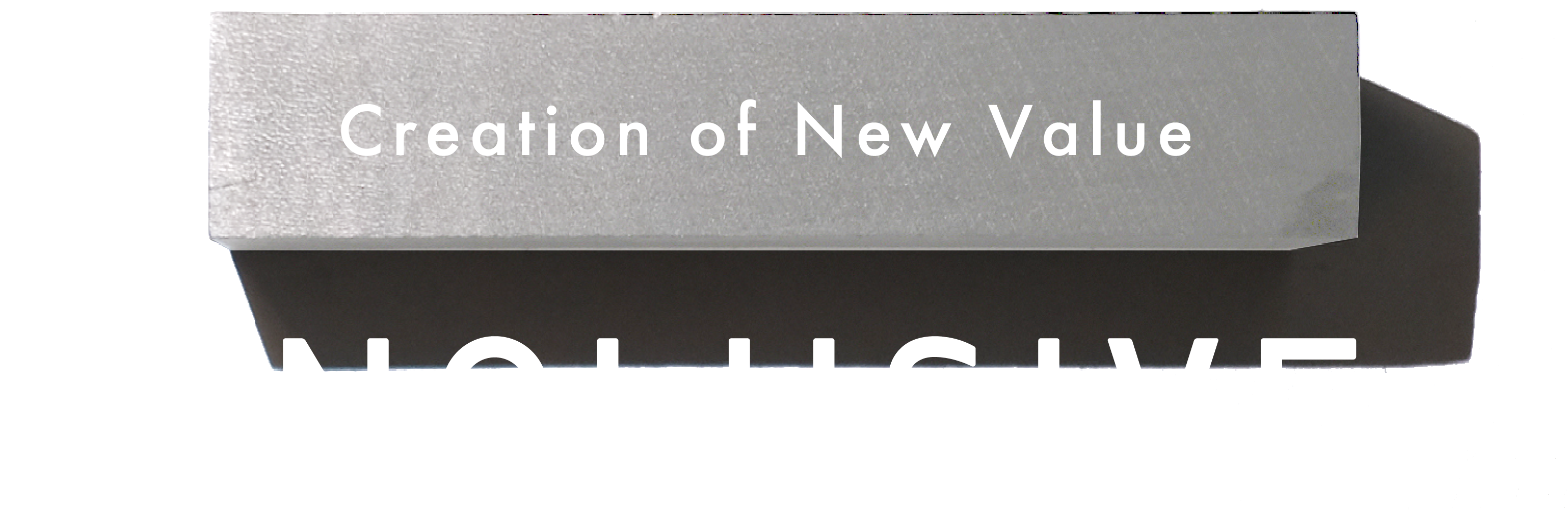ヒトを変え、事業を変え、
そして社会を変える。
数多くのデジタルメディアを成功に導いてきたコンテンツ企画とエディトリアル、そしてクリエイティビティの力で、メディア、広告、食、地域創生、宇宙関連、枠にとらわれない多様な事業領域に、新たな価値を創出する。
それが私たちの存在意義です。
私たちは、才能と個性の多様性を受け容れ、表現の多様性を創造し、
それらをかけ算して多様な価値観を持つ人々にサプライズな体験として届けます。
文化や価値観のギャップを越え、誰もがワクワクする社会を支える存在でありたい。
We’re diverse, but “INCLUSIVE”.